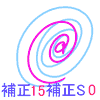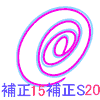※矩形や円、直線、曲線などを描く場合は→<ツールとツールオプション編>のブラシの項目か、<定規編>を参照。
※変更したブラシの設定を保存したい場合は→<ブラシ保存編>を参照
パラメータの数値をキッチリ合わせたい場合は、shiftを押しながらスライダを弄ると良い。
スライダで数値入力したい場合は、
スライダ付近でマウスの左ボタンを押したままキーボードから数値を入力するか、
スライダ付近で右クリックした後、キーボードから数値を入力してEnterキーを押せばできます(ver1.30_script06以降)
※数値が微妙にずれる事がありますが仕様です。内部的には数値が合ってます(「ブラシ設定をコピー」で確認)
ver1.36_script33の20130429版 時点
●サイズ、濃度、ブラシ画像など

【種類】
・「ノーマル」…通常は「ノーマル」のままでokです。
・「文字」…文字ツールとして使うときにこの設定にします。
・「p1」「p2」「p3」「a1」「t1」「t4」…別に説明します→こちら
【描画】…ブラシの描画モードを設定します。
・「通常」…普通。
・「乗算」…ブレンドモード「乗算」で色を塗り重ねられる
・「スクリーン」…ブレンドモード「スクリーン」で色を塗り重ねられる
・「境界」…水彩境界。透明部分と塗りの境を色濃く出来る。
厳密に言うと境界部分が選択した色、その内側が薄くなった色。
薄い部分はレイヤーの透明度固定で薄くしているようです。
※境界の太さや濃さは、ブラシパレットの「境界サイズ」「境界」のスライダから変更可能。
・「加算」…ブレンドモード「加算」で色を塗り重ねられる
・「焼き込み(リニア)」…ブレンドモード「焼き込み(リニア)」で色を塗り重ねられる
・「ハードライト」…ブレンドモード「ハードライト」で色を塗り重ねられる
・「リニアライト」…ブレンドモード「リニアライト」で色を塗り重ねられる
・「ピンライト」…ブレンドモード「ピンライト」で色を塗り重ねられる
・「オーバーレイ」…ブレンドモード「オーバーレイ」で色を塗り重ねられる
・「比較(暗)」…ブレンドモード「比較(暗)」で色を塗り重ねられる
・「比較(明)」…ブレンドモード「比較(明)」で色を塗り重ねられる
・「差の絶対値」…ブレンドモード「差の絶対値」で色を塗り重ねられる
・「ベタ」…元からある描画の色情報を書き換える様に上から塗り潰せる。
ブラシの透明度の重なりは通常の動作と変わらないので、レイヤー上の色の濃淡は残る。
ベタとして使うには、一度白で塗り潰してから使うと良い。(レイヤー上のピクセルの透明度を100%にしてやる。)
・「hsv」…hsvモードの様に色を塗り重ねる事が出来ます
・「なし」…「なし」に設定した上で、混色「ぼかし」のパラ―メータを使うとぼかしツールが作れます。
ただし、「なし」のままだとバケツツール(塗り潰し)が使えないので注意。



左側がブラシ画像をフォルダ分けしてる時にフォルダの一覧が出てくる。
・「all」…フォルダ分けがしてあっても関係なく全ての画像の一覧を表示。
・「/」…一番上の階層にある画像を表示。
※ブラシ画像の追加、フォルダ分けの仕方は→<テクスチャ・ブラシ画像の追加編>
※サムネイル表示で使うには→<ブラシ画像パレット編>
「サイズ」スライダ…ブラシの太さ(px)を変更できます。
「濃度」スライダ…ブラシの濃度(透明度)(%)を変更できます。
「ps不透明度」…この数値を下げると、photoshopの鉛筆ツールのような透明度を下げても均一な塗りができます。
※「濃度」は100にしてから使うと良い。
仮想の別レイヤーを使っているので混色機能は使えなくなります(筆圧曲線 補充 背景色での色は混色できる)
混色を使いたい場合は「ps不透明度」スライダを100にしておくと良い
また、ver1.35_script32の20120630版から付いた「混色 レイヤー」スライダを使えば混色ができるようになります
「間隔」スライダ…ブラシ画像を描画する間隔(%)を変更できます


●テクスチャ

【T効果】…テクスチャをどういう風に描画するかを決定
・「ブラシ濃度」…ブラシの透明度にテクスチャを適用。
塗り重ねればテクスチャは見えなくなる。
※ブラシ濃度の場合、ブラシパレットの「アンチエイリアス」のチェックを切ると
テクスチャのアンチエイリアスも切れるので注意。
・「レイヤー透明度」…(ブラシで描いた範囲内の)レイヤー上の、ピクセルの透明度にテクスチャ適用
塗り重ねてもテクスチャの形状を維持。
・「前景色・背景色」…描画色でテクスチャの描画部分を、背景色でテクスチャの透明部分を塗り潰す。
ブラシで使う時は、混色「細かく」、補充「100」にする事。
バケツで使う時にはツールオプションパレットでパターン「ブラシテクスチャ」にしている事。
左側はフォルダ分けをしている時にフォルダの一覧がでます。
・「all」…フォルダ分けがしてあっても関係なく全ての画像の一覧を表示。
・「/」…一番上の階層にある画像を表示。
※テクスチャ画像の追加、フォルダ分けの仕方は→<テクスチャ・ブラシ画像の追加編>
※サムネイル表示で使うには→<テクスチャパレット編>
「テクスチャ」スライダ…テクスチャの反映度をこの数値(%)で決定します。
この数値を「0」にするとテクスチャ機能がオフ状態と変わらないので注意。
「テクスチャの反転」…テクスチャ画像の白黒を反転させた状態で使います
テクスチャで普段描画していた部分が透明に、透明だった部分が描画部分に変わる。
●混色・ぼかし

※描画部分が存在するレイヤーで混色します。透明度との混色はしないので透明部分では機能しません。(「ぼかし」と「細かく2」は別。)
※混色機能を切りたい場合は、「混色」「混色s」を0に、「補充」「補充s」を100にします。
※「sp不透明度」スライダを使用していると混色機能が使えなくなります。「ps不透明度」スライダは100にしてからお使いください
【混色】…混色の仕方を決定します
・「粗く」…ブラシ円全体で混ざった色を出す。
・「細かく」…ブラシ円の中でもピクセルごとに混ざった色を出す。
なので下にある描画がそのまま引きずられた様な混ざり方をする

 混色「粗く」
混色「粗く」  混色「細かく」
混色「細かく」・「粗く2」
「粗く」との正確な違いは分かりません
予想ですが、透明保護や選択範囲を使用して着色している際、
透明部分からのストロークで描画色が強く出過ぎないようにする為のものかも?
・「細かく2」…この項目だけ透明度とも混ざります
※「細かく2」のままだとバケツツール(塗り潰し)が使えないので注意。
「補充」「補充s」を0、「混色s」を100にして、「混色」スライダの数値を上げると指先ツールになります
※指先ツールとは、既にレイヤー上に描かれている色を指で引きずった様にするブラシです
 →
→ 
この文字列をコピーしてからメニュー欄の「ブラシ」→「ブラシ設定を貼り付け」でブラシが反映されます
「混色」スライダ…既にレイヤー上に描かれている色をブラシの描画色にどれだけ混ぜるか、その量を決める(透明度とは混ざりません)
数値が少ない時ほど色伸びをし、数値が大きい時はねっとりとした描き心地になります。
そして、数値が0だと混色を切っている状態です。
数値が少ない時は少しずつしか下地の色を取得しないのでゆっくりと色が変化するのに対し、
数値が大きいと取得した色がすぐさま反映されるのであまり色伸びしないねっとりとした印象になります
「補充」スライダ…選択している描画色をどれだけブラシに反映するかを決める
「s混色」スライダ…ストロークの開始地点(start)で既にレイヤー上に描かれている色を、
ブラシの描画色にどれだけ混ぜるか、その量を決める(透明度とは混ざりません)
「s補充」スライダ…ストロークの開始地点(start)で、選択している描画色をどれだけブラシに反映するかを決める

↑混色15、補充0、濃度100の場合(要するに「混色」スライダのみの動作)
ブラシ画像が一つ進むごとに下地の色を取り込んでいるのが分かります
「補充」の数値を上げると、この色(下地の色を取り込んだ色)に選択中の描画色を足した色になります
「ぼかし」スライダ…キャンバス上に描かれてる描画をぼかす。(描画をしてからぼかすのでブラシ画像もぼかされたように見える)
そのぼかしの強さを変更できます。
「混α1」スライダ…「混α2」の数値が大きい時に使います
「混α2」で薄くなった描画色の濃度を上げます
※「濃度」スライダで数値を上げても描画色の濃度は上がりますが、
同時に消去部分の数値も上がるので描画のみ数値を上げたい時に使う
「混α2」スライダ…色の混色とは違って、透明度を混色させる為のもの(正確には混”色”ではなく混”透明度”)
レイヤーのα値上で混色動作をさせて透明度をかき混ぜていると予想
数値を上げると透明度が混ざったようになりますが、透明度の濃さ(普通の混色で言うところの「補充」?)を弄れるだけで、
混ざり具合の強さは一定のまま弄れないようです
混色「粗く」の状態で透明度を混ぜている。(「細かく」の状態に出来れば指先ツールも作れそうですが無理っぽい)
数値を大きくすると透明感が増しますが100%塗りつぶし状態にならないため、
下レイヤーの色が透けて見えます。(「混α1」の数値を少し上げればマシになる)
※「筆圧曲線 消去」と似た機能ですが別物です。
「筆圧曲線 消去」はレイヤー上の透明度を減らす(消去)だけですが
「混α1」「混α2」はレイヤ上の透明度を増やす事もします。
あと、混αは筆圧で変化しません

↑で使用した混αブラシ
この文字列をコピーしてからメニュー欄の「ブラシ」→「ブラシ設定を貼り付け」でブラシが反映されます
















 ※色を塗り重ねたい時は別レイヤーで塗ってから結合、を繰り返すと良い
※色を塗り重ねたい時は別レイヤーで塗ってから結合、を繰り返すと良い